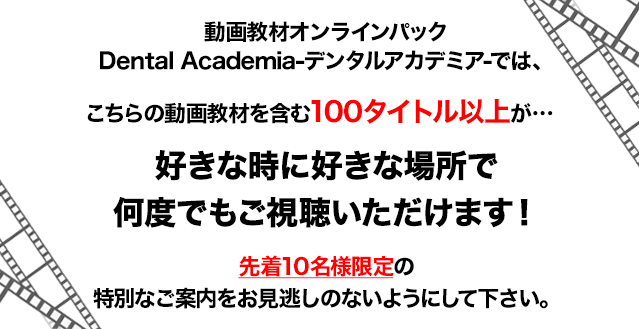はじめまして、こんにちは。
歯科医療総研の山本と申します。
1989年に8020運動が促進されて30年以上が経過し、2016年には80歳以上の50%が20本以上の歯を維持できているという、世界に誇れる達成率となりました。
しかし、一方で歯の不良債権化のようなことが発生してしまっているのはご存知でしょうか。
特に介護福祉の世界では歯があることが逆にリスクになってしまって管理できずに放置されてしまう状況もよく見受けられます。
そして管理できない8020の末路は…急に歯が抜けてしまったことによる誤嚥性肺炎や窒息です。
これはインプラントにおいても同様です。

インプラントは自然歯より歯周炎になりやすいのはご存知かと思いますが、埋入した10~20年後の状況を考えた手術やサポートを行える歯科医師は非常に少ないのが現状です。
もちろん、これを突き詰めるとインプラントの術式のことだけでなく施設や家庭への訪問診療の取り組みが必要になります。

もちろん福祉だなんだと言って、経営的なメリットがないボランティアのようなことをやるべきだと言っているわけではありません。
そもそもなのですが、厚生労働省の発表では2025年に外来患者はピークを迎え、一方で在宅患者数は2040年以降にピークを迎えると見込まれています。

つまり、もう外来患者は縮小傾向になるのですが、在宅はまだまだこの先10年以上増加していくということですので、もはや外来に固執する必要がないのではないでしょうか。
しかも訪問診療は点数が優遇されていることもあり、
1日数件の訪問でも年間1,000万円以上の売上増加が可能で、しかも人件費や交通費などを入れても利益率は40%以上です。

そこで今回、インプラントと訪問診療を組み合わせた患者さんの長期管理法を公開してくれるのが1998年から新潟県長岡市でひまわり歯科を開業している北澤 敦(きたざわ あつし)院長先生です。


医療法人社団ひまわり歯科
理事長
北澤 敦
■プロフィール
1998年、地元である新潟県長岡市にて「ひまわり歯科」を開業。
「外来だけでなく歯科訪問診療などにも尽力している。リコール数を着実に伸ばし、定期メンテナンス患者数は月400名以上、訪問診療件数は200件以上となり、年商は2億5千万円を超え、毎年その数を伸ばしている。
地域の方々からの信頼も厚く、現在では介護施設や行政からの講演依頼も多く高い評価を受けている。
北澤先生は開業当初からインプラントと訪問診療の二刀流を実践する数少ない歯科医師で、インプラントにおいては毎年100本以上で累積1,100本以上の埋入実績を持ち、訪問での診療も月200人以上。
その結果、一医院で年商は2億5千万円を超えており、そのうちの5,000万円は訪問診療による売上だそうです。

しかも、インプラントと訪問診療を組み合わせた治療はここ数年の申し込みが多くなってきており…
●月レセプト数600→1,000以上(2倍弱の増加)
●年自費売上2,500万円→8,800万円(3倍以上増加)
このように、外来も含めたトータルの売上増加にも確実に繋がっているのです。
特にインプラントは訪問でのメンテナンスが可能になると患者さんが安心して申し込めるので成約が爆発的に増加すると言います。
このように北澤先生は訪問診療とインプラントのスペシャリストであり、立地が悪くても、分院を出さなくても、地域医療に大きく貢献しながら売上の増加をさせた成功モデルを作り上げたのです。
とは言っても、本当にインプラントと訪問診療の両立は可能なのでしょうか?
北澤先生が言うには、インプラントが得意でなかったり、まだ訪問診療をやっていない先生でも比較的簡単にできるようになる方法をまとめてあるというので具体的にお話いたしましょう。

まずインプラントなのですが、これは訪問をやっていない先生にも高齢者や将来の身体機能の低下が予測される患者さんに対して持っていてほしい選択肢なのですが、以下を重要視します。
●設計 : 清掃性の良い位置
●手術 : 骨量のある部位に短いインプラント
●骨増生は最低限に:将来的な再手術リスク軽減
●補綴:セメントフリーでメンテナンス性を重視(何かのとき外せる)
※1本インプラントの場合
このように、若い患者さん以外の場合は「清掃性」と「低侵襲」を優先し、機能性を重視した治療計画が求められます。
「審美性重視」「過剰な骨増生」は短期的に美しい治療を可能としますが、将来的な介護やメンテナンスを考慮すると高リスクです。
審美性と清掃性は反比例することが多く、例えば歯の近接位置に埋入するとインプラント周囲の清掃は困難になり周囲炎リスクは増大します。
審美重視で歯肉を厚く整形手術した場合も長期的維持が困難ですし、術後炎症リスクも増加します。
骨増生に関しても絶対にしてはいけない訳ではないですが、一次手術から侵襲が大きくなってきますし介護が必要な時に骨増生部がリスクになる恐れがあります。
ですので、オステオプッシャー使用やANYONEインプラントなどを推奨して極力は骨増生しないインプラントを選択して下さい。
※上顎大臼歯の薄い歯槽骨(1~3mm)でも1~3ヶ月で食事可能にできるテクニックもあります。



そもそもですが訪問診療は土地代や工事代のかからない非常に効率の良い分院展開だとお考え下さい。
嚥下内視鏡や移動車を購入しても400万円程度の諸経費で始められますし、
今からお伝えする方法をやってもらえれば初年度から800万~1,600万円の売上が可能です。
まずは在宅ではなく介護施設への訪問から始めていきます。
実は施設側は歯科医院との提携があると施設加算があり、尚且つ利用者が入院してしまうと施設利用料がとれなくなるというルールがあるので、このあたりを使って入院リスクを減少させる歯科医療を強みに入っていくのが一番有効です。
また、施設は規則正しい生活で、例えば昼食後の1~2時間を使うと効率が良く、必ず決まった時間に食堂に皆さんいるので計画を立てやすいのも特徴です。
もちろん外来では悩みの種になるキャンセルという概念もほとんどありません。
さらに施設の診療で信頼を得ると、施設スタッフや患者さんのご家族がかなりの確率で外来患者になるので、訪問診療をやればやるほど外来も増えるという状態も作ることができます。


訪問先でのインプラントのメンテナンスは周囲炎への対応が主になりますので以下の3段階に合わせた診療をしていきます。
●「初期:継続的に口腔ケア」
軽度の炎症でまだ骨吸収はないので患者さん本人のセルフケアが不十分なケースが多いです。
介護者・施設スタッフへのケア指導とタフトブラシ・歯間ブラシの使用法を伝えるだけでも対応できます。
●「中期:局所除菌~投薬」
このあたりから炎症が進行し、排膿・出血があり骨吸収が始まる次期です。
クロルヘキシジン含有ゲルを訪問時に塗布やデブライドメントをしていきます。
また、噛み合わせからくる歯周炎もこの頃から出ることがあるので過度な咬合力のある患者さんはナイトガードを推奨します。
●「末期:外科処置(インプラント除去も含む)」
骨吸収が進行しインプラントが動揺し炎症・排膿などが起こり感染が全身に波及するリスクが出てきますので、外科処置困難なため抗菌療法として全身投与( 内科医と連携して投薬も)が必要です。
また脱落から窒息のリスクもあるのでインプラント撤去の判断もここでは行う必要があります。

いかがでしたでしょうか?
今回ご紹介したインプラント対応型の訪問診療の導入方法は、これから外来患者が減少して在宅患者が増加していく世の中において…地域医療への貢献と売上増加を同時に行える一番の手段になると思います。
しかし、インプラントのような外科的な処置や、訪問件数の増やし方は、今回の文面だけでは全てお伝えすることが難しいので…
累積1,100本以上の埋入実績と月200件の訪問診療を行っている北澤先生による直接解説をしていただける特別セミナーを開催いたしました。
そしてセミナーの内容を動画教材に収録して特別に公開させていただくことになりました。
そこで、収録内容から今回のご案内しきれなかった、院長先生が得られるメリットの一部をご紹介しますと…

このように、ほとんどの院長先生が知ることのできなかった「インプラント対応型の訪問診療」について、10年以上の実績を持つ北澤先生自らによって120分に渡って語られています。

この先10年以上は増加していくことが見込まれている、介護福祉の世界では通院できなくなる患者さんに対応したインプラント治療ですので、これを知っているのと知らないのでは医業収入に大きな差が生まれるのは間違いないと言えるでしょう。
そこで今回、興味を持っていただいた先生には少しでも安く提供したいと思い79,800円を定価にしたのですが…